「去年より稚魚が高い…」「エサ代も上がった」「それなのに出荷価格は下がっている」。
ここ数年、多くの養殖現場からそんな声が聞こえてきます。
ブリ養殖業界は、稚魚の乱獲・餌代の高騰・価格の暴落・赤潮や高水温といったリスクに常にさらされています。
こうした厳しい環境の中で事業を続けていくには、**「安定した仕組み」と「新しい技術」**を取り入れることが欠かせません。
本記事では、ブリ養殖を持続可能にするための3つの実践戦略を紹介します。
どれも「今すぐできる一歩」から始められる内容です。
戦略1:完全養殖の成果を「利用」して安定供給を実現
完全養殖というと「国の研究」や「大手企業の話」と思われがちですが、
実はその成果を個人養殖業者でも活用できる時代になってきました。
天然モジャコへの依存から脱却し、人工種苗を採用することで、
「仕入れ」「収益」「品質」がすべて安定する可能性があります。
✅ 個人事業主が完全養殖の成果を利用するメリット
① 安定した仕入れ源の確保
人工種苗の普及で、天然稚魚の価格変動に左右されずに計画的な仕入れが可能になります。
② 通年出荷と収益の安定
育種技術により「夏痩せ」が軽減。価格の暴落期を避け、年間を通して販売計画を立てられます。
③ 品質と社会的信用の向上
均質な品質の出荷が可能になり、資源管理にも貢献。認証取得にも有利です。
👉 ポイント:
個人事業主の皆様は、自ら研究を行う必要はありません。
研究機関(水産研究・教育機構など)や大手企業が開発した高性能な人工種苗を採用することが、この戦略の第一歩です。
戦略2:AI・ICTを活用した「スマート養殖」でコスト削減と効率化
労働負担の軽減や生産管理の効率化は、現場にとって喫緊の課題です。
AIやICT(情報通信技術)の導入は、これを解決する鍵になります。
たとえば、AIカメラが水中のブリを自動で撮影し、
「今はエサが足りているか」「成長スピードはどうか」を自動で判断してくれるシステムも登場しています。
こうした仕組みを取り入れれば、経験と勘に頼らない効率的な経営が可能になります。
💰導入コストを抑えるための公的支援の活用
現在、国は「経営体数と生産量の減少」に対応するため、
AI画像認識やローカル5G通信を活用したスマート養殖技術(給餌の自動モニタリング、尾数カウント、魚体サイズ自動測定など)の普及を推進しています。
補助金や実証事業への参加は、導入コストを大幅に削減できるチャンスです。
💡最新の補助金情報は「水産庁 スマート養殖 実証事業」などで検索してみてください。
地方自治体でも独自の支援制度が始まっています。
戦略3:環境変動と事故に備える「3つのリスク管理」
高水温、赤潮、台風といった予測不能な環境変化は、養殖業の最大のリスクです。
これらに備えるための3つの対策を紹介します。
🧱対策1:物理的な被害を防ぐ「設備投資」
高水温や台風による被害は、魚の成長不良や大量死に直結します。
• 浮沈式生簀の導入
海水温が高くなった際や台風時に、生簀を海中に沈められる浮沈式生簀を導入することで、生育環境を安定化できます。
→ 初期投資で後の損失を防ぐ“保険”になります。
📘対策2:環境事故に備える「計画と手順」
赤潮などは突発的に発生します。被害を最小限に抑えるには、事前準備と迅速な対応が不可欠です。
• 手順書の策定と活用
水産庁が提供するGAP(Good Aquaculture Practice)モデル手順書を参考に、
赤潮発生時や水質変化時の行動手順を明文化しましょう。
→ 手順書は「事故対応」だけでなく「信頼の可視化」にも繋がります。
🌊対策3:日常的な「飼育環境の最適化」
健康な魚を育てることが、長期的なリスク軽減につながります。
• 飼育密度を下げた「薄飼い」を徹底し、魚粉代替飼料や固形餌を活用して海域保全に配慮。
• 給餌の最適化と定期的な水質測定を行い、日々の環境変化を記録しましょう。
まとめ|「できることから一つずつ」
これら3つの戦略は、どれも「一度に全部」行う必要はありません。
まずは、あなたの現場で今すぐ始められることを一つだけ選んでみてください。
そして、水産研究・教育機構など公的機関の情報をチェックし、
最新の技術や支援制度を上手に活用していきましょう。
産業横断型の協働(WWF Japan Seriola Initiativeなど)の参加や、
養殖認証の取得も、今後の販路拡大や経営体質の強化につながります。
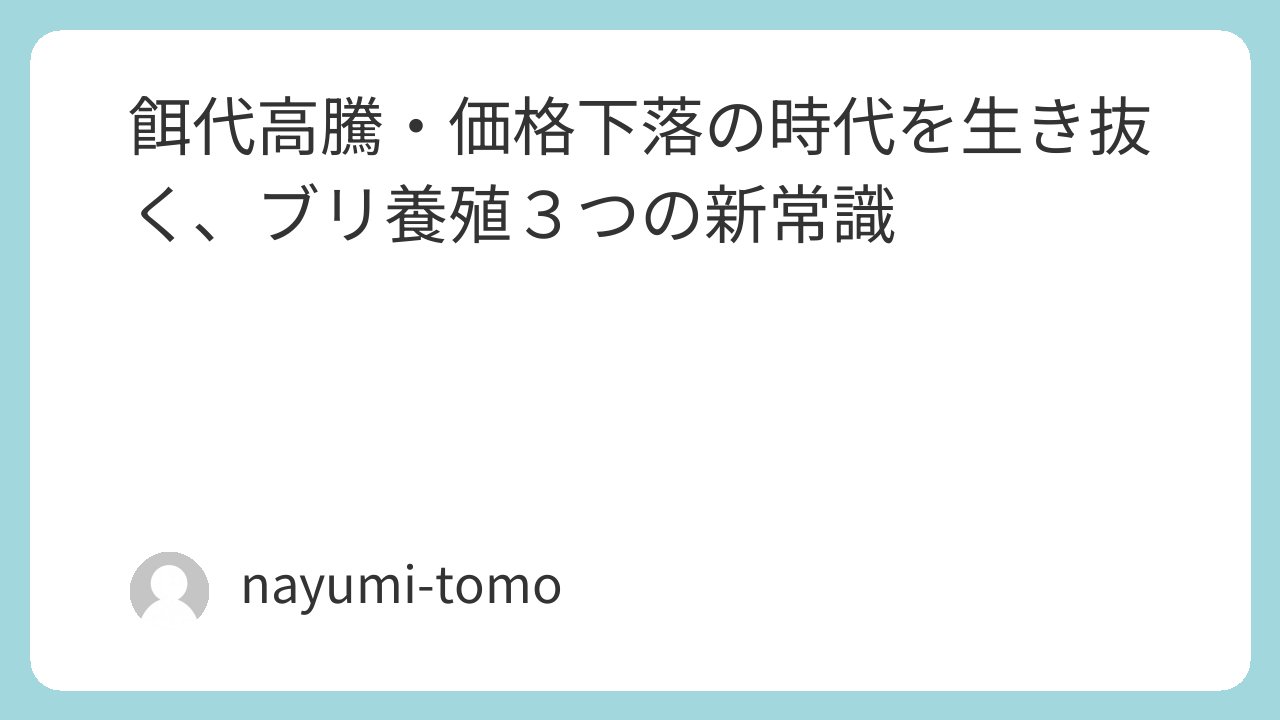
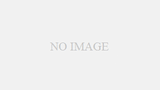
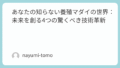
コメント